「績む」こと
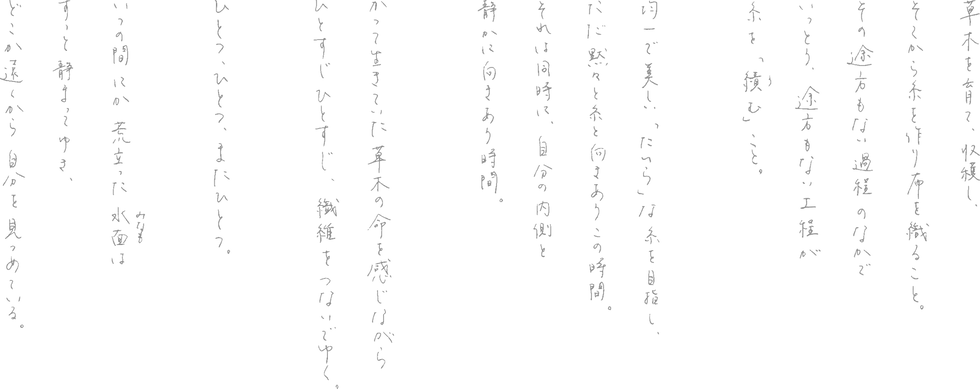
「績む」と「紡ぐ」
屋号の由来にもなっている「績む(うむ)」という言葉。これは、長い繊維の端と端を一本ずつより繋ぎ糸を作ることを指す。私が使うからむし(苧麻)や葛などの繊維は、固く長く繊維同士が絡まりにくいため、手作業ならばそうやって一本一本繋ぐことでしか糸を作れない。昔の日本人の日常着はそういった草木の繊維によって作られており、「績む」作業はとても身近なものだったらしい。
でも、普通糸を作ると言ったら「紡ぐ(つむぐ)」という言葉がまず思い浮かぶ。糸車をカラカラと回して糸を作る–––これは、綿状の繊維を撚りながら糸を引き出す作業。繊維同士が絡まる性質を持っていると、こうやって「紡ぐ」ことができる。こちらの方が「績む」より断然効率が良い。天然繊維から機械で糸を作る方法はこの「紡ぐ」だ。江戸時代以降普及した綿(コットン)は「紡ぐ」ことに適した繊維で、効率的に糸を作ることができたから広まった。だから今「紡ぐ」と言う言葉が一般的に使われているのだろう。
※績み繋いだ糸に撚りをかけることも、「紡ぐ」と言う人もいる。だから、糸を長く取り出すために撚りをかけるにしろ、もう長い糸に撚りをかけるにしろ、糸に「撚りをかけること」が「紡ぐ」なのかもしれない。
※絹の世界はまた違った「ツムグ」「ツムギ」の言葉の使い方があるらしい。

績むとは
「績む」行為は、同じ作業の繰り返し。植物の繊維を指で裂き、裂いた繊維を繋ぎ、糸をためる苧桶に送っていく。天然繊維の心地よい感触を、指に、口に感じながら、右手で撚って、左手で撚って、それから苧桶に送って–––「たいら」な美しい糸を目指し、ただ黙々と繊維と向き合うと、いつの間にか日常生活の慌ただしさに荒立った心がすっと静まっていく。「績む」時間は、私にとって凪のようなもので、自分の内側と静かに向き合う時間だ。
そんな績みの作業で生まれる糸には、機械紡績の糸には出せない美しいニュアンスがある。 均一を目指す中でも生まれる、微妙な太さの違い。 それからからむしの繊維自体の、傷や光沢や色味の違い。それらがなんの変哲も無い平織りの粗い布にさえ得も言われぬ力強さ、美しさを与える。
だから私は績むことが好きだ。繊維と向き合い、糸と向き合い、自分と向き合う。
瞑想のようなこのひとときを、これからも大切にしていきたい。